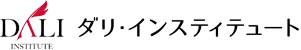ピアノに関するQ&A-アゴーギグやテンポ・ルバートについて
Q:棒弾き(平べったい弾き方)にならないように少しテンポを揺らしたいので、なにかコツがあれば知りたいです。
A:(講師:塩川)まず、演奏されている曲において必ずしも(以下アゴーギグと言います)が必要になるのか、ということを確認しましょう。
そもそも楽曲の速度指定に作曲家が”Tempo giusto”と書いているのならば、リズムの間隔を伸び縮みさせることはあまり正解とならないでしょう。また、「ルバートなしで」や「遅く(速く)せずに」などの指定がある時は必ずその指示に従う必要があります。
それらの例外を除いた場合、ほどよいアゴーギグは曲想を豊かにしてくれます。
アゴーギグの仕方を考える際、必ずその曲の分析、作曲家の時代背景を考えるようにしましょう。
例えばベートーヴェンやハイドンなど、古典的な作曲家の作品においては、だらだらとまどろっこしいテンポの揺れというのはむしろ美しさを欠いてしまうことになります。理由としては、和声構造が比較的シンプルなことや、フレーズの構成がオーソドックスな非和声音で成り立ってることなどが挙げられます。また、時代的にテキスト原理主義的な考えもあったでしょう。
時代が下り、ショパンやリストなどロマン派時代になると、今度は楽譜に書かれていること以上に演奏者の意図を盛り込む必要がでてきます。作曲家自身が名ピアニストであり、自作曲を演奏する際は自身の裁量で聴衆を意識してより自由な演奏を目指したこともあったでしょう。
この時代によく用いられたものに「テンポ・ルバート」という独特なテンポの揺らしがありました。ルバートは直訳すると「盗まれた」という意味であり、その名の通りあるパッセージの速さを借りてきて別のパッセージに加えるというやり方を行います。この際のコツは(私は分かりやすいように「ルバートの法則」と呼んでますが)、フレーズ単位で考えた上でそのフレーズ内の標準速度を0とした場合、ある部分を遅くするとその加減に応じて-1や-2、速くすると+1や+2などとしていって、最終的にそのフレーズ内の総和が0になるように調整すると、無理のない自然なルバートになります。
もし、感性や直感頼りだと不安という場合は、このように論理的に考えるとよいでしょう。