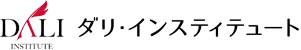ピアノに関するQ&A-本番時のコンディションについて
Q:本番の時がなかなか集中できません。ホールでの響きも慣れないし、客席の物音や前の人の演奏などが頭に流れてきます。本番前の緊張が少なくてもいざ弾き始めると指が固くなってしまいます。
A:基本的に本番の演奏というのは、練習以上の成果は出ないと思った方が良いです。
本番の演奏で指が固くなってしまうとのことですが、緊張すれば必然的に身体は固くなってしまうのである程度は仕方のないことだと思います。ただ、そこまで酷い心境ではないのにも関わらず硬いというのは、練習の段階から既に硬いままの状態で弾いているのかもしれません。
人間の頭は簡単に錯覚しやすく、また自惚れやすくできているそうです。「普段はできている」と思っても客観的にみるとできていなかったりすることは多くあります。つい言い訳を言ってしまいたくなることもありますが、しっかりと事実を受け止め、練習内容の修正を行っていくほかないと思います。
ご質問にもあるように、ホールの響きに慣れないというのは演奏家にとっていつも付きまとう難題です。
まずそのホールでの事前リハーサルの有無でかなり変わってきます。現場でのゲネプロが可能であれば、誰か協力者に客席で聴いてもらい意見を伺ってみて、自分が受けた印象とのギャップの折衷案をとるということもできますが、それでも実際にお客様の入り具合によって響きが変わるため、ある程度は経験に基づいた予測が必要になってきます。
結局のところ、大事なのは現場対応力だと思います。演奏中に舞台上での響きと遠くの壁から反響してくる音、客席の雰囲気などを読んで瞬時にタッチを最適化していく必要があります。何かに気を付ける、というより場数を踏んで、職人的なカンを磨いていくことが重要です。
また、物音や他の演奏など外部に意識が向いてしまうとのことですが、それはそれで一つのアドバンテージになります。
客席の物音が聞こえたという事実を演奏中でも気づけるという事は、良い意味でとらえると自分の音が会場でどう響いているか、また自分の演奏でお客様がどういう反応を示しているかを観察する能力があるということです。
ピアノ奏者は基本的に自分の所持している楽器で演奏できない為、ホール内に響く音量やタッチ、ペダリング等を本番の演奏中に確認しながら微調整をする必要があります。
自身に没頭できる性格のタイプであれば普段通りに近い演奏ができますが、会場の空気や音の響きをあまり認識ができていないというデメリットがあるように感じます。
ちなみに、とある名ピアニストは客席の雰囲気を観察しながら、曲のダイナミクスやルバート、速度などを調節していたそうです。自分自身のもつ特徴を長所とするか短所とするか、決めるのもまた自分自身です。